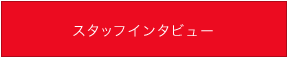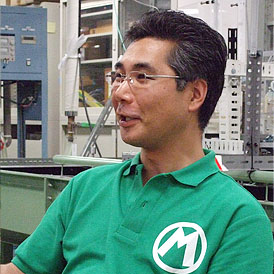函館密着型科学者、本村真治さん
取材・執筆:小原 果穂・池本 葉梨子(北海道教育大学函館校 マスコミ研究会)
本村先生は函館高専卒、函館高専勤務の、まさに函館密着型科学者といえるような方だ。その先生の函館と科学、そしてSSH(サイエンス・サポート函館)への思いとは一体?
科学を仕事に

「エンジニア」の響きに憧れ、15歳で親元を離れて函館高専に入学した。在学中は寮生活を送りながら、部活に打ち込んだ。入学と同時に始めた軟式テニスは、熱心な練習の甲斐あって4年の時に高専の大会でダブルス北海道制覇を成し遂げる。卒業後は「仕事は世の中を知るためにある」との思いから北海道を離れ、関西の大手電器メーカーに就職したが、地元への思いは強く残っていた。
転機は25歳の時に訪れた。母校である函館高専から教員をやらないかとの打診を受け、5年ぶりに函館に戻ることを決めた。しかし用意されていた席は専門外の『流体工学』。「0からではないが0.1からのスタートでした」と当時を振り返る。高専に戻ってからの2年間は、しばしば学生と共に授業を受け、流体工学や教師としての勉強をした。教授の難しい講義内容をかみくだいて学生に説明することで、自らの理解も深めていった。また、自身の学生時代には普及していなかったパソコン操作を習得するのにも苦労したという。「パソコン操作の指導を受けても、何を言っているのかわからなかった。当時の苦労が、感覚でわかる説明を心がけるきっかけになりましたね」と語る。
SSHを立ち上げる
 函館高専では以前から子どもを対象に、年に数回の公開講座を開いていた。市民が科学や技術に触れる機会をもっと増やそうとの思いか、有志の同僚ら共に、平成15年から公開講座を年間30回ほどに増設した。さらに、地域共同テクノセンターを介して地域や企業と連携を深めていった。こうした高専の活動が大きくなるにつれ、函館市全体の活動にしていこうとの思いが強まっていった。その実現に向け、JST(独立行政法人 科学技術振興機構)へ補助金申請の構想を市に相談したところ、未来大でも同じようなアイディアが出ていることがわかった。これがきっかけとなり、キャンパスコンソーシアム(市内高等教育機関の連携組織)をベースに、高専と未来大が共同で函館市全体の科学技術コミュニケーション活動をスタートさせた。
函館高専では以前から子どもを対象に、年に数回の公開講座を開いていた。市民が科学や技術に触れる機会をもっと増やそうとの思いか、有志の同僚ら共に、平成15年から公開講座を年間30回ほどに増設した。さらに、地域共同テクノセンターを介して地域や企業と連携を深めていった。こうした高専の活動が大きくなるにつれ、函館市全体の活動にしていこうとの思いが強まっていった。その実現に向け、JST(独立行政法人 科学技術振興機構)へ補助金申請の構想を市に相談したところ、未来大でも同じようなアイディアが出ていることがわかった。これがきっかけとなり、キャンパスコンソーシアム(市内高等教育機関の連携組織)をベースに、高専と未来大が共同で函館市全体の科学技術コミュニケーション活動をスタートさせた。
「高専は、小中学生を中心とした一般市民に対する小規模な公開講座に取り組んできました。一方、未来大には大きな科学イベントの企画運営を得意とする学生さんや教員がたくさんいます。それらをあわせることで、活動の幅を函館全体へ広げていけるのではと考えました」
『科学を文化に』を合言葉に、SSHの活動は年々広がっている。SSHの活動対象は市民全体であり、子どもに限定しているわけではない。現在、公開講座の3割はCAD講座や史跡巡り、西部地区探索など大人を対象としたもので、8月に催される『はこだて国際科学祭』のAエリア(西部地区)には、大人も楽しめるイベントが多数ある。このように、SSHは子どもから大人まで広く市民に科学にふれる機会を提供する。
函館と科学のこれから
「学生のうちに見たり、聴いたりした体験の中から、将来進む道を選んでいくものでしょう。科学もその選択肢のひとつですが、残念なことに、今の函館には、科学や技術に触れる機会はそう多くはありません」と、函館の問題点を指摘する。日常でそれらに触れる機会を提供することが、SSHの目的のひとつだ。
「科学にふれるチャンスがなければ、その道に進むことはありません。SSHの活動への参加がきっかけとなって、科学や技術が選択肢のひとつになれば、と思っています」
科学祭だけでなく、科学網によるネットワークや、科学寺子屋での体験を通じて、より多くの子どもに科学や技術に興味を持ってもらうこと。それが“科学人”の育成につながるのだ。
最後に、先生の夢を聞いてみた。「函館青少年科学館の館長になることです」とにっこり笑って答えて下さった。
「でも、箱ものだけ作っても意味がない。まずはSSHの活動が函館に広まって、認知されないと」
笑顔から一転して、真剣な表情でそう話す先生の目には、科学という文化が根付き、多くの“科学人“を生み出す函館の姿が見えているのだろう。
2009年6月取材