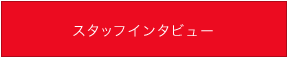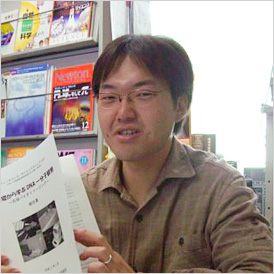子どもと共に科学を楽しむ
取材・執筆:向平 侑加(北海道教育大学函館校 マスコミ研究会)
北海道教育大学函館校で教鞭をとる松浦俊彦先生は、バイオテクノロジーのスペシャリスト。生物が持つ機能を実社会に役立てるための研究を行っている。子どもたちに理科の面白さと有用性を実感してほしいという願いもあり、「サイエンス・サポート函館」に携わることとなった。
松浦先生×理科
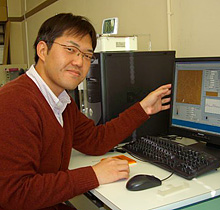
小学生のころは理科が好きではなかったし、とりわけ生き物が苦手だったという松浦先生。しかし「モノはどうして落ちるのか」というような自然現象には興味があった。理科、特に物理の面白さに気づいたのは、中学生になってから。中学校の理科の先生の教え方は決して上手いとは言えなかったけれど、授業の内容や先生との会話が新鮮だったという。
中学校に入ってから理科が好きになる子供が多いのは、日本の理科教育の特徴だ。というのも、小学校までには無い少し踏み込んだ科学を、科学のスペシャリストに初めて教えてもらうからなのだとか。
日本の理科教育における課題の例にもれず、高校に入ると理科嫌いに。中学校では楽しかった理科の授業が、高校で突然難しく感じ苦手になってしまった。「大好きだった理科で赤点をとってしまって…さすがにびっくりしましたよ」と当時を振り返る。しかし高校3年生のある時、受験勉強のためじっくり考えていると突然、今まで難しいと思っていた理科の仕組みがひも解くようにわかった。
その後大学、大学院で物理の研究を進めていくうちに、大嫌いだった生物学分野に興味を持ち始めた。「科学者が研究を突き詰めていくと、最終的には“宇宙の誕生”と“生命とは何か”という2つのテーマに行き着くんです。そして僕は後者をやろうと決めました」
子ども×理科
 現在、附属函館小学校で理科教育のディレクターを任されている。子どもたちが理科に興味を持って取り組めるような授業づくりの方法を、現職の教員に指導する。
現在、附属函館小学校で理科教育のディレクターを任されている。子どもたちが理科に興味を持って取り組めるような授業づくりの方法を、現職の教員に指導する。
最近では、新幹線が走る仕組みについてプラレールを改造して教えた。「子どもたちが理科の授業で勉強していることが、実社会に応用されて役立っていることを知ってもらうことが大切です。教育大学の先生として、幅広く、子どもたちが科学に触れる機会を与えたい。理科の面白さやその有用性を伝える授業をするのも使命」と語る。
「理科教育の現場に立って、子どもの“理科離れ”を感じることはありますか?」という問いに、「僕は“理科離れ”を信じていないんです」と一言。最近テレビのクイズ番組が流行っているが、回答者が間違えてもすぐに解説してくれるので、視聴者もクイズに参加できる。しかし松浦先生は、「それは時間をかけてじっくり考えることを嫌う“思考離れ”の表れでは?それがいつの間にか“理科離れ”に転換されてしまっているように思います」と答えた。
サイエンスショーを見た子どもが、自分で真似してやってみても失敗することが多い。サイエンスショーでは、失敗する可能性が低い実験を万全の準備をして行っているのだから、成功するのは当然だ。しかしその準備には科学的思考力が必要だし、やってみないと実感することはできない。「今の子どもたちにとって、“やってみる”ことは敷居が高いのかも知れません。でも失敗してもあきらめず、じっくり考えてやってみることが大切です」と語る。
“科学空間”を目指して
 今年(2009年)8月末に行われた科学祭では、五稜郭タワー内アトリウムの会場統括をしていた。サイエンスショーや科学屋台をゆっくり見物する暇もなく、裏方に徹し会場をうまくまとめた。「興味があって来た人、たまたま通りかかった人、理由はさまざまかもしれませんが、大勢の方々が科学に触れる機会を提供できて良かったです」と科学祭を振り返る。「五稜郭タワー、その空間そのものが“科学”に染まっていたと思います。次回も科学の空間に浸れるような科学祭を目指したいですね」と来年の科学祭に向けて抱負を語る。
今年(2009年)8月末に行われた科学祭では、五稜郭タワー内アトリウムの会場統括をしていた。サイエンスショーや科学屋台をゆっくり見物する暇もなく、裏方に徹し会場をうまくまとめた。「興味があって来た人、たまたま通りかかった人、理由はさまざまかもしれませんが、大勢の方々が科学に触れる機会を提供できて良かったです」と科学祭を振り返る。「五稜郭タワー、その空間そのものが“科学”に染まっていたと思います。次回も科学の空間に浸れるような科学祭を目指したいですね」と来年の科学祭に向けて抱負を語る。
最先端の科学は、誰もが学校で勉強してきたことが基本になっている。「理科なんて暗記だけでつまらない」という子どもたちに、SSHを通して「理科ってホントにおもしろい」ということを伝えること。大人も子供もみんながサイエンスを楽しむことができる環境づくりをすること。これが今、松浦先生が目指す“科学空間”だ。
2009年11月取材