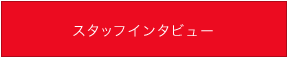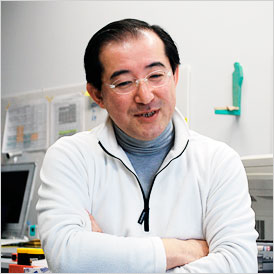科学祭を編集する
取材・執筆:松田 夏海(北海道教育大学函館校 マスコミ研究会)
木村先生は、大学教員になるまで、首都圏の映画・演劇・音楽・美術など様々なジャンルのイベント情報を網羅する情報誌の編集者をしていた。そして、現在では情報デザインの研究を行っている。科学祭では、編集者時代の経験を生かし、イベントの企画・運営を担当するディレクターとして活躍している。
編集とは?

そもそも「編集作業」とはどのような仕事なのだろうか?先生に教えて頂いた。
「まず、イベントっていうのは、ただ漠然と並んでいるだけでは魅力的には映らないんですね。編集とは、簡単に言うと、集められた素材を組み合わせて全体像が魅力的に一望にできるようにすること。これは僕の専門である情報デザインに関係しています。例えば、はこだて国際科学祭の編集ではアートディレクターの高田さんによるマークロゴや色彩設計や空間設計を各イベントに適応させていく。印刷物の特性やサイズ、設置場所や対象ユーザにあわせて、函館に適応させていくっていうのも僕の仕事ですね」。
先生いわく、編集作業で一番重要なのは「素材の良さ」とのことだ。「科学祭は素材が素晴らしいから、編集はとてもやりがいがある」と嬉しそうに語ってくれた。
また、編集のしやすさ、情報の発信という点でも、人口およそ30万人の函館はイベントを行うのに「最適な規模」であるという。
これ以上大きくなると情報が行きわたらなくなる可能性が高まる。逆に少ないと素材そのものが不足しまう。イベントを行うには10万人前後の人々に告知できることが大切だというが、はこだて国際科学祭2009では北海道新聞の広告タブロイド版としてプログラムを13万部配布することが出来た。
また、イベントを行う人がお互いの顔を知っているというのも魅力的だ。コミュニケーションがとりやすく、アイデアが出しやすい。面倒な手続きがいらず、フットワークが軽いことは、大きな強みになりえる。
本来は、科学祭のようなイベントは科学館がないと実現が難しいはずだが、函館では大学や研究所の存在がそれを実現させている。
函館は、まさに科学祭を行う土地として有利な要素を兼ね備えているようだ。
科学とアート
 「科学」と聞くと、多くの人はまず実験の光景を思い浮かべると思う。それはなんとなく複雑で、手ごわいイメージがないだろうか?しかし、木村先生が科学祭であつかう科学はそうではない。先生はサイエンス・サポート函館(SSH)において「アートの力」を生かして、「科学」のイメージを新たなものにしようと考えている。
「科学」と聞くと、多くの人はまず実験の光景を思い浮かべると思う。それはなんとなく複雑で、手ごわいイメージがないだろうか?しかし、木村先生が科学祭であつかう科学はそうではない。先生はサイエンス・サポート函館(SSH)において「アートの力」を生かして、「科学」のイメージを新たなものにしようと考えている。
イベントは観客が「かっこいい」と思えることがとても大切だ。デザインや色遣いが美しく、イベントが滞りなく進められる。「見ていてかっこよくないと人は集まらないし、理解は得られない」と先生は考えている。その「かっこよさ」の表現のためにアートはとても重要な役割を担う。
2009年の国際科学祭は「環境」をテーマに行われた。その展示会場には、ニューヨーク在住のアーティストであるインゴ・ギュンター氏が制作した地球儀をモチーフにした作品『ワールドプロセッサー』が展示された。地球をモチーフにした美しい作品を見ながら、環境などのグローバルな問題について考えてもらうのが目的だ。
先生に「科学とアート」のつながりについて尋ねると興味深い話をしてくれた。 「アートが直接的に人の生活に作用することは確かにあまりないかもしれない。けれどアートは、人の頭にかなり強い刺激を与えるものです。アートから受けた刺激が影響して、科学技術に対する理解が促進される。日常の生活の見え方に変化を生むこともあると思いますよ」。
「科学とアート」の融合というのは今までにもあらゆるところで試みられてきている。しかし、それが本当に上手くいった例は実は少ないそうだ。 それでも、先生の言うように、目には見えないところでアートが私たちの生活に影響を与えているのだとしたら、「科学」と「アート」を積極的に結びつけていくことは重要な意味を持っていると思う。
2010年の科学祭のテーマは「食」。先生は昨年と変わらず、いや、それ以上にイベントにアートを取り入れ、科学とアートの新たな可能性を示そうとしている。
日常の科学
 科学技術に関心を持つことは、よりよい日常生活の手助けになる。
科学技術に関心を持つことは、よりよい日常生活の手助けになる。
例えば、生物や遺伝に関する知識があれば、病気になったときに、身体に何が起こっているのか理解しやすい。遺伝子組み換え食品への接し方を考えながら、毎日の食事に配慮することもできる。
しかし、実際には、人々が科学的な知識と日常生活のつながりについて考えることはほとんどない。学校で科学を学んでいるときは「それがどんな意味を持つのか」「なんの役に立つのか」意識していないことが多いのが現状のように思う。
先生は「SSHのイベントに参加することで、日常生活で科学の功罪を意識するきっかけになって欲しい」と話す。
そして「今以上に、日常生活の中で科学への理解が進むことで、バランスのとれた新しい常識が生まれる」という希望を持っているそうだ。
最後にSSHの今後についてたずねると、「科学祭がありふれた日常的な事になり、あえてイベントを行う必要がなくなるくらいを目指したいですね」と笑いながら答えてくれた。
2009年12月取材