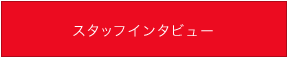食糧と人間の未来
取材・執筆:吉家 寿明(北海道教育大学函館校 マスコミ研究会)
高橋是太郎教授(58)は北海道大学大学院水産科学研究院で『資源利用学』という領域を研究している。主な研究内容を大別すると、リン脂質や糖脂質などの複合脂質に関わるもの、サケの肉の色を非破壊的に測定する装置の開発(道立工業試験場との共同研究)、そして水産物の「コク」(キリン協和フーズとの共同研究)に関わるものだ。
クオリティ・オブ・ライフに貢献

まずは、リン脂質に関わるものについて。リン脂質は興味深い物質で、リン酸や塩基と脂肪酸、すなわち水とよく交わるものと交わりにくいものが二層構造をなしている。そのリン脂質の内、水産系リン脂質で他の物質(がんを抑制するような物質)を包み込むと、その物質が体内に吸収されやすくなったり、体内で新しい機能を発揮するのだという。この研究が発展していくと、「末期がんになり激ヤセしてしまう悪液質という病態を緩和できるかもしれない。そしてがん患者の生活の質(クオリティ・オブ・ライフ)の維持に貢献できることになるかもしれない。」と高橋氏は考えている。
続いては、サケの肉の色を非破壊的に測定する装置の開発。二十年近く前に、光ファイバーを内臓した測色色差計を応用して、サケの肉の赤色度を数値化しようとしたが、ハード、ソフトの両面で挫折したそうだ。しかし、3年ほど前より道立工業試験場の情報システム部の方々に本格的に取り組んでいただき、国の支援を得て、漸く実現のめどがつきつつあるとのことであった。
インスタント食品がもっと美味しくなるカモ?
 そして水産物の「コク」についての研究。高橋氏は「身欠きニシンのコク」に注目した。そのコクは何の成分に由来するのであろうか。そして、熟成中に発生する物質が結合して「コク」が生まれるのではないか、と考えたのであった。その物質は日常の様々なシーンで活躍することだろう。高橋氏は「インスタント食品」の例を挙げた。
そして水産物の「コク」についての研究。高橋氏は「身欠きニシンのコク」に注目した。そのコクは何の成分に由来するのであろうか。そして、熟成中に発生する物質が結合して「コク」が生まれるのではないか、と考えたのであった。その物質は日常の様々なシーンで活躍することだろう。高橋氏は「インスタント食品」の例を挙げた。
「インスタント食品に絶対的に欠けているものが何かといえば、それがコクなんだよね。そのコクを加えれば、例えばシチューのように長時間かけてつくった料理のうまさが引き出せてもっと美味しくなるはず。」と語った。われわれ貧乏学生にとってはインスタント食品の代表格であるカップラーメンは日常に深く溶け込んだものといっても過言ではない。「コク」が加われば本当に毎日食べても飽きないものになるかもしれない、と筆者は考えてしまった。
しかし、先生はその先を行く。「食糧不足、食糧不足っていうけれど、私はそうは考えない。そりゃぁ、今ある(食べている)食物をこのまま生産して食べていくのであれば、不足するのかもしれない。でも、まだ食物としてまだ認識されていないようなものでも、コクなどといったように、さまざまな改良を重ねることによって食物としての新たな側面を見出すことが可能なんじゃないかな。つまり、このコクなどの物質を、今までとてもじゃないけれど食べられないといわれてきたものに加えることによって、実はたくさんの食糧が地球上には存在するはずなんだよね。」
ブレーン(頭脳)の産地、函館
そんな先生は、函館を「ブレーン(頭脳)の産地」と考えている。「ブレーンの産地であることは間違いないけど、流出しちゃうからね。それをどう食い止めるかってことかな。それから価値観の違いが大きいかな。知識や教養が増やすことは初めは修行なんだけど、それを超えたところの楽しさというのかな、そこが勉強の楽しさでもあるからねぇ。そのギャップを科学祭のようなイベントで埋めることができたら良いね。」
さらに日本全体については、「欧米では家族そろってゴールデンタイムにサイエンス番組を見るというのは、普通にあるらしいんだけど、それが日本ではなかなかできないよね。ゴールデンタイムはお笑いかスポーツかって感じだと、(科学を家族で楽しむような)そういう雰囲気も作りづらいよね。」と考えているようだ。
ユーモアのある高橋先生とのインタビューは終始笑顔で進んだ。出身地も岩手(筆者も同郷)ということで、一段と親密感が増した。個人的な感想としては、近い将来カップラーメンに「コク」が加わる日を心待ちにしている。
2009年9月取材